ネコが画家に愛される理由
なぜ画家たちはこれほどまでに猫を愛し、描きたがるのでしょうか。この記事では、美術史に名を刻む有名な猫の絵画を辿りながら、画家たちが猫の何に魅了され、インスピレーションを受けてきたのか、その理由を紐解いていきます。
詳細を見る


2025年12月1日~2026年2月28日開催
本サイトのリニューアル後初となる特別展です。 本展では、古今東西の芸術家を魅了してきた「猫」をテーマに、ジャンルを超えた多様なアートが集結。愛らしくも神秘的な猫の姿を、5名の気鋭アーティストが描きました。あなたの人生を楽しく豊かにする一枚との出会いをお楽しみください。 【参加アーティスト】伊藤清子、原田ちあき、溝口まりあ、山田貴裕、吉田瑠美(50音順)
※当初会期は2025年12月20日に設定していましたが、好評につき2026年2月28日まで延長します
”だるまを被った猫が幸せを連れてきてくれますように”
”猫は切なさのアイコン”
”この美しき月に捧げましょう!”
”孤高に立つ1匹の獣、心の中は燃えるような紅”
”おかまいなく。彼は毅然としていた”
”猫が金魚をくわえる夢から生まれました”
”神戸市立博物館大ゴッホ展に合わせ制作”
”親戚のスコティッシュフォールドがモデルです”
”最後は肉球を触らせてくれました”
”くにゃくにゃな感じ、伝わりますか”

なぜ画家たちはこれほどまでに猫を愛し、描きたがるのでしょうか。この記事では、美術史に名を刻む有名な猫の絵画を辿りながら、画家たちが猫の何に魅了され、インスピレーションを受けてきたのか、その理由を紐解いていきます。
詳細を見る
幼い頃からスケッチブックを手放さず、動物や風景の“そのものらしさ”を描くことに自然と向き合ってきた吉田瑠美さん。絵本作家、画家・イラストレーター、そして中国武術の講師という多彩な顔を持ち、現在は京都と東京、そして台湾を行き来しながら創作を続けています。今回の猫をモチーフにした特別展では、台北の友人宅に暮らす猫をモデルに、3日間寄り添うように滞在して描いた2点の作品を出展。柔らかく形を変える猫の魅力、武術が制作に与えた影響、台湾との深いつながりなど、創作の背景を伺いました。 幼少期と絵を描く原点 ――小さい頃はどんなお子さんだったのでしょうか? 絵との関わりを教えてください。 吉田 幼い頃から、どこに行くにも小さなスケッチブックを持ち歩いていて、待ち時間があれば自然に何かを描いていました。描くことは「コミュニケーションの手段」でもあり、「世界を見つけていく方法」でした。物心つく前から紙とペンさえあれば静かに楽しんでいるような子どもだったと思います。 ――“描くのが得意だ”と意識した瞬間はありましたか? 吉田 小学校1年生のときの写生の授業で、校庭の花をとても上手に描けたことがきっかけでした。好き勝手に描くのとは違い、「見て写す」ことが自分は得意なのだと気づいた瞬間でした。 幼少期を過ごしたニューヨークでの1枚(右は弟) ――青山学院で幼稚園から短大まで過ごされていますが、学生時代はどのように表現と向き合っていましたか? 吉田 学校では友人や先生に恵まれ、のびのびと絵を描いたり文章を書いたりを続けていましたが、家では実は“武術少女”でした。10歳のときテレビで見た中国武術に魅了され、週6日、社会人チームに混ざって練習するほど本気で取り組んでいました。 ――短大で芸術学科を選ばれた理由は? 吉田 14、5歳の頃、絵の学校には行きたいとは思っていたのですが、「絵はスポーツの後でもできるけど、スポーツは絵の後にはできないよ」と武術の先生にも言われ、まずは武術に真剣に取り組むことにしました。2008年の北京五輪のジュニア有望選手にも選ばれていましたが、20代で怪我で競技を引退してからは太極拳や気功も学び、指導者の道を選びました。 勝ち負けの意識がとても希薄でいい選手ではありませんでしたが、10代に真剣に稽古をして自分に集中し続ける修行時代を持てたことや、20代の頃から、子供から年配の方まで幅広い世代の方やお仕事の方に出会い、さまざまな世界に触れ続けることができたのが自分の財産です。進学した青山学院女子短期大学の芸術学科は少人数制で、先生方も“社会に出てからは作家同士”という目線で接してくださり、その学びが今も支えになっています。 京都への移住と“プロ”の道が開いた瞬間 ――プロとして歩む転機はいつ訪れたのでしょう? 吉田 29歳のとき、京都へ移住しました。ゆったりとした時間の中で久しぶりに絵を描いたところ、それを見た夫が「僕はこれ、好きだな。絵がいっぱい増えたら、個展を開いてみたら?」と勧めてくれたんです。個展を開いてみるとたまたま編集者の方が来てくださり、動物園の絵本の仕事を依頼されました。展示を続けていると、浄土真宗のカレンダーの仕事をいただいたり、肖像画のお仕事をいただいたり、不思議なご縁が重なって。いつかはそうなったらいいなとは思っていましたが、ありがたいことに、気がついたら絵のお仕事が増えていました。 京都に移住した頃の1枚 ――動物を描く際に心がけていることは? 吉田 「そのものらしさ」が出るまで描き込むことを心がけています。武術では対象をそのまま見て受け取り、繰り返し練習して身体に落とし込むのですが、その姿勢は絵にも通じています。対象に“なりきる”ように向き合うことで、動物らしさが自然と出てくると感じています。 ――画材の使い分けにはどんな基準が? 吉田 絵本の場合は編集者と話し合いながら作品の世界観に合う画材を選びます。自身の作品を制作する際は、その瞬間の気持ちを最も込められるツールを選びます。今回出展した《音を見つめる》《夢のかたち》はアクリルガッシュを使用し、細い線を重ねやすい点を活かしました。ほかにもクレヨン、色鉛筆、ペンキ、油彩など幅広い素材を使いますが、そのときに自分が一番思いを込めやすいと思うツールを選んでいます。ただ、これまでは水彩をあまりやってこなかったので、今後は挑戦したいと思っています。 《音を見つめる》※作品ページはこちら 《夢のかたち》※作品ページはこちら 多彩な活動:絵本作家・画家・武術講師という3つの顔 ――今回の猫作品は台湾の友人宅の猫がモデルと伺いました。 吉田 はい。何度か遊びに行ったことのある友人宅の猫を書かせてもらいました。最初は数時間だけスケッチしようと思っていたのですが、猫があまりリラックスしてくれず……。そこで「泊まらせてほしい」とお願いし、3日間一緒に過ごしました。ご飯を食べたり、同じ部屋で寝起きするうちに猫が心を開いてくれて、自然体の姿を書けるようになりました。 ――猫の“どんな姿”を描きたかったのですか? 吉田 作為的なポーズではなく、リラックスした瞬間や自分の時間を楽しんでいる姿を描きたかったんです。猫は柔らかく、骨格からは想像できない形に、まさに“液体”のように形を変えます。その柔らかさや「ふにゃ」っとした表情を大切にしました。 ――絵本作家、画家・イラストレーター、武術講師。それぞれをどのように両立しているのでしょう? 吉田 自分でも説明が難しいほど自然な流れで続いています。武術は10歳で始め、実はそのときの指導者が夫になったのですが(笑)、その夫とともに教室を運営していました。4年半前に夫が突然亡くなり、働き方も変化しました。現在は絵の仕事の比率が増えていますが、武術を通して学んだことは自分の核でもあり、お教室の方々にも恵まれ、大切に思っています。最近はラジオパーソナリティやエッセイの仕事もいただき、「『今度はこれをやってみたら』と天から言われているのかな」と思いながら一つひとつの仕事に挑戦しています。 ――武術は制作活動に影響していますか? 吉田 大いに影響しています。こう見えて意外と体力があるので、壁画の制作で10~12時間作業しても自分の体を上手くコントロールできます。また、長い槍や剣という道具を扱うときに先端に意識を込める練習をするのですが、その経験が、普通の30センチくらいの筆はもちろん、壁画で長い筆を使うときでも役立っています。また、知らない土地に行ったり、いろいろな人に会うことも多いのですが、どんな環境も楽しんでしまうところも、武術の修行時代を通して得たものだなあと感じます。 演舞中の様子 台湾との深い結びつきと、広がる創作活動 ――台湾との関わりはどのように始まったのでしょう? 吉田 私の祖父が台湾人で、もともとルーツはありましたが、大人になるまでに一度しか行ったことがなく、よく知りませんでした。決定的だったのは、映画監督の弟が制作した日台合作映画で、主人公の女の子の“ゴーストペインター”を依頼されたことです。夫を亡くした直後で、映画の世界は初めて。できるかなと戸惑いもありましたが、夢中で絵を描くうちに、日台のアーティストの友人がたくさんできて、台湾とのつながりが一気に深まりました。今は台湾文化を紹介するラジオ番組のパーソナリティも務めています。 台湾で壁画を制作中の様子 ――台湾での反応は日本と違いますか? 吉田 とても違います。台湾の方は「これは好き」「これは好きじゃない」と初対面でも率直に伝えてくれるんです。作品単体だけでなく、前作とのつながりや文脈まで含めて理解しようとしてくれる点が印象的でした。 ――今後挑戦したいことは? 吉田 来年は海外の仕事も決まっていて、台湾以外の国にも広げていきたいです。小さい頃アメリカに住んでいたので日常会話はできますが、作品を説明できるレベルの語学力を高めたいと思っています。もっと自由に動き、誰かの役に立てるアーティストになりたいです。 ――最後に、「月刊美術プラス」の読者へメッセージをお願いします。 吉田 美術は敷居が高いと感じる方もいるかもしれませんが、いろいろなことがある日々の中で、それぞれの痛みを和らげて幸せな気持ちを与えてくれるものだと思っています。今回、猫の特別展に参加できてとても光栄です。温かい気持ちになれる作品を届けられたら嬉しいです。 ――ありがとうございました。
詳細を見る
猫を中心に描かれる作品で知られ、SNSでも高い人気を誇る画家・山田貴裕さん。精緻な筆致で描く猫たちは、柔らかな毛並みや瞳の光を繊細に捉え、思わず触れたくなる存在感を放っています。現在は会社員として翻訳業に携わりつつ、制作活動を続ける“二足のわらじ”スタイル。手描きの原画を基盤に、デジタル技法も取り入れることで独自の猫表現を追求しています。本記事では、幼少期から画家として歩み始めるまでの道のり、猫を描く理由、出展作《ゴッホ猫》《チャンスを掴む猫》《Emerald(エメラルド)》の裏話、そして未来の展望までを伺いました。
詳細を見る
鮮烈な色彩と、一度見たら忘れられない表情豊かな猫たちを描く日本画家・溝口まりあさん。伝統的な岩絵具や金箔を用いながら、高級車「フェラーリ」の顔料を取り入れるなど、独自の技法で現代の「猫画」を追求する。出品作3点に込められた制作秘話や、意外すぎる画材へのこだわり、そして猫たちへの深い愛情について、たっぷりと語っていただきました。 「レオナルドまりあ」と呼ばれた少女と、運命の「猫」 ――今回の特別展「猫・ネコ・CAT」で、溝口さんの描く猫たちの表情の豊かさに心を掴まれました。溝口さんご自身、昔から猫がお好きだったのですか? 溝口 はい、猫以外にも幼い頃から生き物が大好きで、犬、ウサギ、ニワトリ、ザリガニ、ハムスター、カブトムシ……本当にいろいろな動物と暮らしてきました。その中でも、中学1年生のときに初めて飼った「リュー」という猫との出会いが決定的でした。彼はなかなかの曲者で(笑)、決して己を曲げない、誇り高い猫だったんです。 リュー 私の人生のターニングポイントにはいつも猫がいて、大学院2年生の頃に現在の作風――猫をモチーフにした作品を描き始めたきっかけも、そのリューちゃんでした。現在は、5歳の「雷電(らいでん)くん」と、3歳の「金時(きんとき)くん」という2匹の猫と一緒に暮らしています。彼らは私の作品の大切なモデルでもあります。――やはり身近な猫たちがモデルなんですね。溝口さんは、いつ頃から日本画家を目指されたのでしょう? 溝口 画家になろうと決めたのは小学4年生の頃です。幼稚園の年少の頃からアトリエ教室に通っていたのですが、毎回スケッチブックを1冊使い切ってしまうほど描くのが大好きで。先生からは「レオナルド・ダ・ヴィンチ」にかけて「レオナルドまりあ」なんてあだ名をつけられていました(笑)。 日本画の道に進むと決めたのは高校2年生のときです。展覧会で伊藤若冲の『群鶏図(ぐんけいず)』の実物を見る機会があったのですが、あまりの迫力と色彩の美しさに衝撃を受けて、涙が止まらなくなってしまって……。「私もこんなふうに、時代を超えて後世に感動を伝えられる作品を描きたい」と強く思い、日本画を専攻しました。 伝統的な技法と新しいアイデアの融合 ――今回出品いただいた3点の作品は、どれも猫たちが生き生きとしていて、まるで人間のような感情を感じさせます。 溝口 今回の3点に共通するテーマは「堂々と己を貫く、誇り高い心」です。猫って、こちらが「大好きだよ!」と愛情を伝えても、「はいはい、そこ置いといて」みたいな感じで、自分のペースを絶対に崩さないんですよね(笑)。その素直で嘘のない感情表現は、人間が心の奥底に持っている感情と共通するものがあると思うんです。私は猫の姿を借りて、そんな「感情」そのものを描きたいと思っています。 ――1点目の作品《美しき月に捧ぐ》は、夜空の下で猫が気持ちよさそうに歌い上げている姿が印象的です。 《美しき月に捧ぐ》※作品ページはこちら 溝口 これはオペラをイメージして制作しました。特にビゼーの『カルメン』とイタリアのカンツォーネ『オー・ソレ・ミオ』からインスピレーションを受けています。猫にとっての太陽は「月」なんじゃないかと思い、美しい月を讃えて高らかに歌う、堂々とした姿を描きました。モデルは「ブリティッシュショートヘア」という、がっしりとした体型の猫です。 ――背景の夜空の「青」と、月の「金」のコントラストが本当に美しいですね。この深みのある青は、日本画ならではの色なのでしょうか。 溝口 はい。背景の青は主に2種類の岩絵具を使っています。月の周りの明るい部分は粒子の細かい「瑠璃色の岩絵具」を、下の暗い層には粒子が大きめの「緑がかった群青色の岩絵具」を使用しました。さらに、グラデーションを深めるために「薄墨」を何層も重ねています。粒子の粗い岩絵具がキラキラと光を反射するのは、油絵やアクリルにはない日本画特有の美しさですね。月には伝統的な純金箔を使い、イタリアのフレスコ画と日本画の要素を融合させました。 ――よく見ると、上げている手の「肉球」が銀色に輝いていますね。 溝口 実は今まで、作品の中で肉球を描くことはあえて避けていたんです。でも今回は、手を大きく広げて歌うポーズなので、思い切って描いてみました。この肉球、実は「プラチナ」を使っているんです。グレーの猫の肉球って、ちょっと黒っぽくてツヤツヤしていますよね。その質感を出すために、墨を塗った上からプラチナ泥(でい)を塗り重ねて、ふっくらとしたツヤを表現しました。銀箔だと時間が経つと変色してしまうことがありますが、プラチナは変色しないので、永遠にこの輝きが続くのです。 ――続いて2点目の《プライド》。鋭い眼光の黒猫と、燃えるような背景の赤が強烈なインパクトを放っています。 《プライド》※作品ページはこちら 溝口 この作品は、タイトル通り「孤高に立ち、決してブレない心」を持つ猫をイメージしました。実はこの背景の赤、あの高級車「フェラーリ」の塗装に使われている顔料を使用しているんです。 ――えっ、フェラーリですか!? 日本画に車の塗料を使うというのは聞いたことがありません。 溝口 そうですよね(笑)。偶然ご縁があってこの顔料を手に入れる機会があったのですが、見た瞬間にその赤の美しさに感動してしまって。フェラーリというブランドが70年以上かけて探求し、進化させ続けてきた「赤」。その歴史へのリスペクトを込めて、日本画に取り入れたいと思いました。 ――伝統的な岩絵具と、現代の車の顔料。合わせるのは大変だったのでは? 溝口 ものすごく大変でした。この顔料、水で溶いてから時間が経つと「膨潤(ぼうじゅん)」といって、粒子が膨らんでしまう性質があるんです。溶きたてだとサラッと塗れるのに、時間が経つとパサパサになってひび割れてしまいます。そして、車の塗装は何層も重ねて初めてあの色が出るので、どの色を重ねればフェラーリの赤が一番美しく発色するか、半年ほどかけて実験を繰り返しました。 完成した絵は、見る角度によって赤の中に黄金のような輝きが見え隠れします。ぜひ実物で、その複雑な色の深みを感じていただきたいですね。 ――3点目の《おかまいなく》。タイトルと、片手を前に出したポーズがユニークで思わず笑ってしまいました。 《おかまいなく》※作品ページはこちら 溝口 このモデルは、我が家の金時くんです。彼は撫でられるのは好きなんですが、タイミングにこだわりがあって(笑)。私が撫でようと手を伸ばすと、「今は結構です」と言わんばかりに、そっと手を挙げて私の手を制止するんです。その毅然とした態度を見て、「自分の意思をしっかり持っていて素晴らしいな」と感心してしまって。たとえ愛する飼い主であっても、嫌なときは上品にお断りする。その凛とした姿を描きました。 金時くん ――背景の茶色の部分に、独特のシワのような質感がありますね。 溝口 これは「揉み紙」という技法です。和紙を手で揉んでわざとシワや凹凸を作り、裏打ちをして固定しています。こうすることで画面に立体感が生まれ、光が当たったときに複雑な陰影ができるんです。 また、日本の気候は湿度の変化が激しいので、紙を揉んで「あそび」を作っておくことで、伸縮による劣化を防ぐ効果もあります。偶然生まれたシワの模様は二度と同じものができないので、その一期一会の表情も楽しんでいただければと思います。 ――3作品とも、猫たちの「目」の力が凄まじく、見つめ返されているような感覚になります。目の表現には特別なこだわりがあるのでしょうか。 溝口 目には必ず金泥や金箔、最近ではプラチナ箔を使って輝かせるようにしています。仏像の「玉眼」のようなイメージですね。光の当たり方で見え方が変わるので、朝見るのと夜見るのとでは表情が違って見えるはずです。 また、《おかまいなく》はこっちを見ているのですが、実は私の描く猫たちは、基本的には鑑賞者と完全に目が合わないように描いています。猫にとって直視は“敵対”の合図なので、あえて視線を少しずらすことで、人間と猫が適度な距離感で共存している様子を表現しています。左右の瞳孔の位置も微妙に変えていて、これは歌舞伎の「睨み」のように、魔除けや幸福を招く意味を込めているんです。 ――繊細かつ勢いのある「髭」も印象的です。 溝口 髭は、一番集中力を高めて描く最後から2番目の工程です。下書きなしの一発勝負で、息を止めるようにして一気に線を引きます。髭動き一つで猫の感情や気配が決まるので、とても緊張しますね。金泥で描いた髭の下に、さらに細い筆で影を描き足して立体感を出しています。和紙の凹凸があるので筆が取られやすいのですが、失敗できないので真剣勝負です。 スランプ知らずの制作論と、意外な「昆虫愛」 ――これだけエネルギーに満ちた作品を描き続けていて、スランプに陥ることはないのですか? 溝口 ありがたいことに、筆が止まったことは一度もないんです。むしろ描きたいテーマや試したい技法がありすぎて、時間が足りないくらいで(笑)。普段はアトリエで無音の中で集中して描いていますが、音楽をテーマにした作品の時は、その曲を延々とリピートして、時には自分で踊ってポーズを確認しながら描くこともあります。また、常に新しい表現の「実験」をしていて、今回のフェラーリの顔料もそうですし、「いつか使えるかも」というアイデアのストックがたくさんあるんです。 ――制作の合間のリフレッシュなどは? 溝口 生き物を見るのが一番の癒やしですね。動物園に行ったり、実は昆虫も大好きで……多摩動物公園の昆虫館にある温室で蝶を眺めたり、標本の即売会に行って美しい昆虫の標本を買ったりもします。「どうしてこんな形に進化したんだろう」と造形の不思議に感動する時間は、絵のインスピレーションにも繋がっています。 ――最後に、「月刊美術プラス」の読者や、今回初めて溝口さんの作品に出会う方へメッセージをお願いします。 溝口 私の作品を購入してくださる方は、玄関に飾ってくださることが多いんです。金箔を使っているのでドアを開けた瞬間にパッと明るくなりますし、黒猫は古来より「魔除け」や「招き猫」の意味もあるので、「我が家の守り神」として迎えてくださるようです。もちろん、リビングでも廊下でも、ふと目が合った時に元気がもらえるような場所に飾っていただけたら嬉しいです。 今回のウェブサイトの特別展で、もし「この猫、気になるな」と心惹かれる作品があったら、それはきっと、皆さんの心の中にいる「猫」――自分らしくありたいという感情――が共鳴したのだと思います。ぜひ、あなただけの誇り高い猫を見つけてみてください。 ――ありがとうございました。 アトリエで制作中の様子 カッパドキア(トルコ)にて
詳細を見る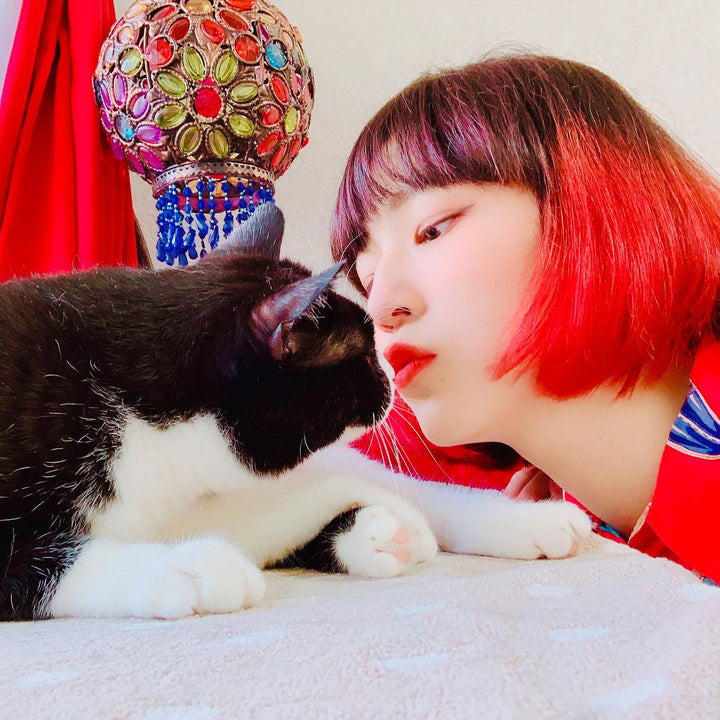
イラストレーター・漫画家として活動しながら、自らを「よい子のための悪口メーカー」と名乗る原田ちあきさん。人間のマイナスな感情や痛みを、どこかカラフルでユーモラスに描き出す作風で知られています。今回「月刊美術プラス」の「猫の特別展」に出展した新作『大親友は今もここに』では、猫と金魚の関係を通じて“生と死の淡い境目”をやわらかく見つめています。猫を“切なさのアイコン”と呼ぶ原田さんに、その作品の背景と創作の源について聞きました。
詳細を見る
柔らかな表情でこちらを見つめる猫。その顔の奥には、見る人の心をほぐす不思議な力があります。日本画家・伊藤清子さんは、そんな猫の魅力を日々の暮らしの中からすくい取り、描き出しています。今回の「猫特集」では、縁起物の“だるま”と猫を組み合わせた新作《猫かぶり−だるまさん》を出展。自然と絵を描き始めたという幼少期から今に至るまでの歩み、猫への深い愛情、そして来年に控える個展への思いをうかがいました。
詳細を見るSIGN UP
会員登録をしていただくと、①購入をスムーズに行える(情報入力の手間が省ける)、②会員限定の特典や情報を受け取れる、③購入履歴やお気に入り商品を管理できる、といったメリットがあります。
会員登録はこちら